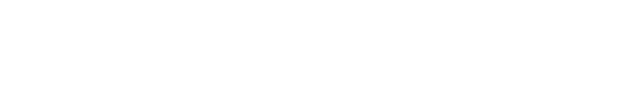リハビリテーションの自主トレーニングメニュー 肩関節障害
肩関節障害の自主トレーニング
1. 肩関節障害の概要
肩関節は非常に柔軟で複雑な構造を持つため、負荷や使いすぎ、外傷などで障害が発生しやすい部分です。肩関節障害には、肩の痛みや可動域制限、筋力の低下などが含まれます。主な原因としては、肩関節周囲炎(いわゆる「五十肩」)、腱板損傷、肩インピンジメント症候群などがあります。
2. 自主トレーニングの役割
自主トレーニングは、リハビリテーションを進めるうえで非常に重要な役割を果たします。次のようなメリットがあります。
- 筋力の維持・強化:障害の影響を受けている肩の筋肉を再度強化し、肩関節を支える力を向上させます。
- 柔軟性の改善:適切なストレッチや運動で肩の可動域を広げ、拘縮や硬さを防ぎます。
- 痛みの軽減:筋肉や靭帯が健康な状態を保つことで、痛みの緩和が期待できます。
- 再発防止:筋力や柔軟性を高めることで、再度の肩の損傷や痛みを予防します。
3. リハビリの重要性
専門家によるリハビリテーションは、自主トレーニングだけではカバーできない点を補完します。理学療法士や医師が関与することで、次のような点が強調されます。
- 正確な診断と評価:専門家が肩の障害の状態を正確に診断し、適切なリハビリテーションプランを立てます。
- 安全な運動指導:無理のない範囲で正しいフォームや運動方法を指導し、二次的な損傷を防ぎます。
- 進行管理:肩の回復状況を定期的に評価し、必要に応じてトレーニングや治療を調整します。
4. 効果的な自主トレーニングの例
肩関節障害の自主トレーニングにおいて、肩甲骨、胸椎、そしてインナーマッスルを動かす体操は、それぞれ重要な役割を果たします。これらの体操を行うことで、肩関節の動きをスムーズにし、痛みを軽減し、再発予防にも繋がります。
いくつかの自主トレーニングを紹介します。
実施前に注意すべきを3つポイントをあげます。
1 自主トレーニングは、実際に理学療法士とリハビリテーションをやっていく中で、動作を確認することをお勧めします。
2 反動をつけてやらないでください。
3 動作で痛みが出る場合は、やめてください。
自主トレーニングは、初級(このページ)、中級、上級と3段階に分けて進めていきます。
初級)
主に肩関節周囲炎(四、五十肩)などの肩関節障害のリハビリテーション治療において、1)肩関節の動きを改善するための運動療法をすること、2)日常生活での肩関節に負担のかかる動作を避けることが非常に大切になります。
肩の関節は、大きく分けて「肩甲上腕関節」と「肩甲胸郭関節」の2つがあります。肩関節の動きを理解することは、リハビリテーションの効果を高めるために重要です。以下に、それぞれの関節について説明します。
1 肩甲上腕関節
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩甲上腕関節とは、肩甲骨の関節窩(かんせつか)と上腕骨頭が接する部分で、肩の動きを大きく支える関節です。肩甲上腕関節の大きな可動性を支えるためには肩腱板筋の働きが重要です。肩腱板筋とは、肩甲骨と上腕骨をつなぐ4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の集合体です。
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩腱板筋は、上腕骨頭を肩甲骨の関節窩に引き寄せることで、肩関節の安定性を維持する役割を担っています。これらを求心性と言い、中級で肩腱板筋のトレーニングの紹介の際に詳しく解説します。
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
2 肩甲胸郭関節
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩甲胸郭関節は、肩甲骨と胸郭(肋骨および胸椎)によって構成される関節です。肩甲骨の動きは肩関節の可動性を補助し、スムーズな動作を支えます。特に、腕を挙げる際には「肩甲上腕リズム」と呼ばれる協調運動が重要であり、上腕骨と肩甲骨が一定の割合で動くことで、効率的な運動が可能になります。このリズムが乱れると、肩関節に過度な負担がかかりやすくなります。(中級以降で詳しく解説します)
また、この関節の機能は長時間のデスクワークによる不良姿勢と深い関係があり、姿勢の崩れが肩甲骨の動きを制限し、筋肉の緊張(こり)や痛みの原因となることがあります(後述)。
実際に3つの自主トレーニングを紹介します。
★肩の可動域訓練(コッドマン体操)
コッドマン体操は、肩関節を大きく円を描くように動かす体操で、肩関節周囲の筋肉を柔軟にし、血行を促進する効果があります。
この体操は肩関節の可動域を広げ、肩周りの筋肉の血流を改善させるので、痛みの軽減に繋がります。
コッドマン体操

- 足を肩幅程度に開きます
- 肩の力を抜き、痛い方の腕を前に垂らしながら、ゆっくりおじぎします
- 身体を前後に揺らし、腕を振り子のように動かします(30秒)
- これを10回繰り返します
コッドマン体操が肩甲上腕関節・肩甲胸郭関節に及ぼす作用
1. 肩甲上腕関節への作用
・ 重力を利用して関節の圧迫を軽減
→ 肩の筋力を使わず、上腕骨頭が関節窩内で自然に動く(モビライゼーション効果:求心性)
2. 肩甲胸郭関節への作用
・ 肩甲骨のリズミカルな動きを促進(肩甲上腕リズムの回復 ※肩甲上腕リズムの詳細については、自主トレーニング中級で説明)
→ 肩甲骨が自然に上下・前後・回旋することで、肩の動きがスムーズになる
・肩甲骨周囲の筋肉の緊張を緩和
・肩甲骨の可動性を高め、肩関節全体の動きを改善
★肩甲骨ストレッチ
肩甲骨は、肩関節の動きを支える重要な骨です。肩甲骨がスムーズに動かないと、肩関節の動きが制限され、痛みが出やすくなります。肩甲骨ストレッチは、肩甲上腕関節の可動域を広げ、安定性を高めると同時に、肩甲胸郭関節の可動性を向上させ、肩甲骨周りの筋肉を柔軟にするといった作用があります。
- 姿勢を整えて座る。 両肩に小指・薬指を乗せる。
- 指先が肩から離れないように気をつけながら、
- 肘で大きな円を前から後ろへ描くようにして肩を後ろに回す。(10回)
★胸椎伸展ストレッチ
背中が丸くなる(胸椎屈曲:猫背)と、肩甲骨が前に傾き(前傾)外側に広がります(外転)(いわゆる巻き肩)。その結果、肩関節の位置がずれることにより、肩甲骨と上腕骨の「協調リズム(※中級で詳しく解説します)」が崩れて、可動域が制限されます。(→腕が上がりにくくなります:下左図)
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
猫背姿勢とは、胸椎の屈曲によって肩甲骨が前傾・外転した不良姿勢のことを指します。デスクワーク、うなだれ姿勢が長時間続くと胸椎の動きが硬くなり、肩甲胸郭関節の可動性が制限され猫背(・巻き肩)になりやすくなります。
猫背による肩甲骨の不適切なポジションを改善するには、胸椎を伸展させるストレッチが効果的です。これにより肩甲骨が自然に後傾・内転しやすくなり、巻き肩も改善され「良い姿勢」を保ちやすくなります。(上右図)
①座りながらできる「胸椎伸展ストレッチ」を2つ紹介します。
- いすに浅めに座り、脚を腰幅に開く。
- 肘を膝の上に置き、おへそをのぞき込むように背中を丸くする(息を吐く)。
- 肘を膝から離さずに、胸を前へ突き出すように背中を反る(息を吸う)。
②座りながらできる「胸椎伸展ストレッチ」
こちらは頚椎のコンディショニングにも、とても重要になります。デスクワークの方は、是非実践してみてください。
頚椎は両手で抱えて、腰椎は反らさないで、両肘を天井につきあげると胸椎が伸びます。
こちらで、初級は終了となります。ここまで読んでいただいた方、お疲れ様でした。
できるようになりましたら、中級に進んでください。