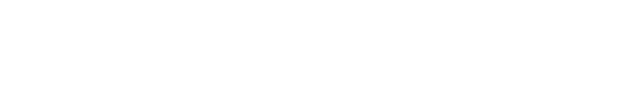肩のリハビリテーション:自主トレーニング (中級編)ステップアップ版
肩関節周囲炎(四、五十肩)の自主トレーニングについて、初級、中級、上級と段階別に分けて説明しています。こちらは中級の頁になります。
・運動療法の中級レベル:初級で肩関節の動きが広がってきた段階で、さらなる肩関節の動きの拡大、肩甲骨の動きの拡大、肩の安定性を向上させるトレーニングを進めていきます。
初級編で肩の動きが広がってきましたら以下の運動をしていきましょう。
★イス引き挙上運動
- 机の前に座り、肩の力を抜きます。
- 両腕を伸ばしたままイスを後ろに引き、身体を前に倒します。
- 限界のところで10秒間止め、元に戻します。
- これを10回繰り返します。
この運動は、肩まわりの筋肉や関節をやさしく伸ばすことで、肩の動きの改善につながります。また、肩甲骨の動きを良くすることで、肩こりや痛みの軽減も期待できます。
「初級編のトレーニング」や「イス引き挙上運動」により肩の動きが広がってきましたでしょうか?
さらに肩の動きを拡大させるためには、肩腱板筋の働きが重要です。ここからは、初級編の復習になります。肩腱板筋は肩甲骨と上腕骨をつなぐ4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)から構成されており、上腕骨頭を肩甲骨の関節窩に引き寄せることで肩関節の安定性を維持する役割を担っています。これを「求心性:下図の黄色矢印」といいます。
求心性とは、肩甲上腕関節を動かす際に上腕骨頭が肩甲骨の関節窩にしっかりと収まっている状態を指し、これが保たれることで肩甲上腕関節の動きがスムーズになります。そのため、求心性は肩関節の機能において非常に重要です。
肩腱板筋
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩の求心性のイメージ図
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩腱板筋(インナーマッスル)トレーニング
インナーマッスルとは、深層にある筋肉のことを指します。肩関節を安定させるインナーマッスルは、肩腱板筋になります。肩腱板筋が弱いと肩関節の動きが不安定になってしまい(求心位がとれなくなり)、肩関節や肩関節周囲に痛みが生じやすくなります。
肩腱板筋(インナーマッスル)トレーニングは、肩関節の安定性を高めるために行います。
★インナーマッスルエクササイズ(内旋・外旋)
- 胸を張り、肘を屈曲にします。
- (内旋)ゴムを内側に向けてひねるように動かします。
- (外旋)ゴムを外側に向けてひねるように動かします。
- これを10回繰り返します。
※肩の内旋には、肩甲下筋がインナーマッスルとして重要です。
※肩の外旋には、棘下筋、小円筋がインナーマッスルとして重要です。
★インナーマッスルエクササイズ(外転)
- 胸を張って肘を伸ばして立ちます。
- ゴムの片側を動かす方の反対の足でふみます。
- 腕を外側へ約こぶし3つ分広げます。
- これを10回繰り返します。
※肩を横に挙げる「外転」の動きでは、肩の奥の筋肉(棘上筋)と、表面の筋肉(三角筋)が主に働きます。
この筋肉を鍛えることで、肩の安定性や動きのスムーズさが向上します。
肩甲上腕リズムについて
初級編でも述べましたが、肩関節は大きく分けると肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節の2つの関節で構成されています。肩の動きを広げていくためには、この肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節が共に動くこと(協調リズム)が大切です。
腕を挙げる動作では、肩甲上腕関節だけでなく、肩甲胸郭関節(肩甲骨の動き)も連動して動く必要があります。この協調的な動きは「肩甲上腕リズム」と呼ばれます。
肩甲上腕リズムとは、腕を180°挙げる際、肩甲上腕関節で120°、肩甲胸郭関節(肩甲骨の動き)で60°動くことを指し、その比率は2:1になります。この肩甲上腕リズムにおいて重要な役割を果たしている主な筋肉として前鋸筋と僧帽筋があります。
肩甲上腕リズム(下記より引用)
Carvalho, Stefane Cajango de, et al. "Snapping scapula syndrome: pictorial essay." Radiologia Brasileira 52 (2019): 262-267.
レントゲン写真でみる肩甲上腕リズム
| 肩甲上腕リズム 良好 | 肩甲上腕リズム 不良 |
右側のレントゲンでは、肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節の動きの比率が1:1となっており、正常な肩甲上腕リズム(通常は2:1)が崩れています。これは肩甲上腕関節の可動域が制限されており、いわゆる「拘縮肩」の状態を示しています。
★肩甲骨の上方回旋について
肩関節を屈曲(腕を前方に挙げる)させる際には、肩甲骨が上方回旋(肩甲骨の下部が外側かつ上方に回る)する必要があります。この肩甲骨の動きを支える主要な筋肉が「前鋸筋(ぜんきょきん)」です。
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
前鋸筋は、肩甲骨と肋骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨の動きと安定の両方に関与します。
この筋肉が働くことで、肩甲骨が肋骨にしっかりと固定され、腕を動かす際にも肩甲骨の安定性が保たれます。
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
肩甲骨の上方回旋に関与する筋肉(主動筋)
① 前鋸筋
-
特に 下部にある線維が上方回旋に強く関与
-
肋骨から肩甲骨内側縁へ付着
-
肩甲骨を外側・前方に引っ張りつつ、肩甲骨の下部を外上方へ回す ★1
② 僧帽筋(そうぼうきん)
-
上部にある線維:肩甲骨を引き上げる ★2
-
下部にある線維:肩甲骨を引き下げつつ内側方向に引く ★3
肩甲骨の上方回旋の動きは、前鋸筋と僧帽筋との協調運動(★1−3)による働きで起こり、肩関節の動きをサポートする役割があります。
つまり、肩関節を動かすためには、肩甲骨の上方回旋の動きが必要不可欠であり、前鋸筋トレーニングは非常に重要なエクササイズになります。(上級編にも繋がります)
【補足】肩甲骨の上方回旋(上腕骨の外転動作)
ヒューマン・アナトミー・アトラスより引用
前鋸筋トレーニング
1.仰向けに寝て、両腕を天井に向かって挙げます。
2.片方の手を天井に向けて持ち上げていき、肩を床面から離します。
5~10回を1セットとして、1日2~3セット行います。
前鋸筋の作用を再確認!
手を前に出す運動(前方リーチ・パンチ動作など)のとき、前鋸筋はこう働いています。
① 肩甲骨の外転
-
肩甲骨を背骨から外側に引く動き
-
肩甲骨が胸郭に沿って滑るように移動
→ 手を前に突き出すとき、肩甲骨が前に出る必要がある
② 肩甲骨の上方回旋
-
腕を上に挙げるときに必要な動きだけど、前方に突き出すときも僅かに関与
→ 肩関節の可動域を補助し、動作をスムーズにする
③ 肩甲骨を胸郭に固定
-
肩甲骨が浮かないように胸郭に貼り付けておく
→ 力が腕や手にしっかり伝わるようになる