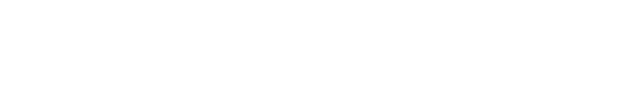膝のリハビリテーション:自主トレーニング(初級)
変形性膝関節症の自主訓練について、初級、中級、上級と段階別に分けて説明していきます。
こちらは初級の頁になります。
(注意)
リハビリテーションの自主訓練は、痛みの軽減や関節の可動域を維持・改善するために非常に重要です。ただし、痛みが強い場合は無理をせず、医師や理学療法士と相談しながら進めてください。
変形性膝関節症の初期症状
初期症状として、膝の痛みや膝をまっすぐ伸ばしにくくなる(伸展制限)ことがあります。
中年以降、膝の痛みを抱えるほとんどの方が変形性膝関節症へと進行し、一度診断されると、ほとんどのケースで変形が進行します。
そのため、初期段階から伸展制限の改善に取り組むことが大切です。
膝関節の構造と動き
膝関節は、大腿骨(太もも)、脛骨(すね)、膝蓋骨(お皿)の3つの骨で構成されています。膝の動きには、大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)が重要な役割を果たします。この筋肉は、膝蓋骨を経由して膝を伸ばす力を伝えます(下図:赤矢印)。
膝蓋骨は、テコの支点のような役割を果たし、筋肉の力を効率よく膝に伝える働きをしています。その結果、膝蓋骨がスムーズに動くことで、脛骨をしっかり伸ばすことができます(下図:黄色矢印)。
しかし、膝蓋骨の動きがスムーズでないと、膝の曲げ伸ばしがうまくいかず、痛みや違和感の原因になることがあります。そのため、膝蓋骨の動きを適切に保つことが重要です。
ヒューマン・アナトミー・アトラス2025 より引用
膝蓋骨の周囲には、「膝蓋上滑液包」や「膝蓋下脂肪体」があります。これらの動きが悪くなると、膝蓋骨の可動性が低下し、その結果、膝関節全体の可動域が制限される原因となります。
そのため、膝蓋上滑液包や膝蓋下脂肪体のマッサージやストレッチを行い、膝蓋骨の可動性を改善することが非常に重要です。
膝関節周囲の組織とその影響
中瀬 順介 (著) 『膝エコーのすべて』日本医事新報社、2020、20ページ より引用
◎膝蓋上滑液包(膝蓋上嚢)について
膝蓋上滑液包(膝蓋上嚢)は、膝のお皿の上に位置する「滑液包(関節や腱の周囲にある液体を含んだ小さな袋状の組織)」で、膝の動きを円滑にし摩擦を軽減する働きがあります。
Procreate にて作図
膝関節で炎症が起こると、関節液が増加し、水が溜まった状態(以下:水腫)になります。この状態は、エコー画像(下に示す)で確認することができます。水腫があると滑液包(特に膝蓋上嚢)が膨らみ、膝関節の動きが制限されてしまいます。
(補足)近年では、膝の水腫に対する治療やリハビリの進歩により、水腫を抜かずに対応できるケースが増えています。また、水を抜く処置には再発や感染のリスクがあるため、慎重に行われるようになっています。
◎膝蓋下脂肪体について
膝蓋下脂肪体は、 膝のお皿の下にある脂肪組織で、膝の曲げ伸ばしをスムーズにする役割があります。エコー画像で膝屈曲時に大腿骨と脛骨の間のスペースに移動し、伸展時にはスペースが無くなり押し出されている動きの様子が下に示すエコー画像で確認できます。
Procreate にて作図
以下では、実際に膝蓋骨の動きを出す自主訓練3つを紹介します。
できるようになったら、中級に進んでください。
A 膝蓋骨の上下、左右へのストレッチ
目的:膝蓋骨周囲の柔軟性改善
1.膝を伸ばして座ります。
2.膝蓋骨を上下、左右に動かします。
各方向へ10回程度繰り返します。
B膝蓋上嚢へのマッサージ
目的:膝蓋骨上方の柔軟性改善
1.膝を伸ばして座ります。
2.膝蓋骨のすぐ上の組織を指で上下方向に動かします。
20-30秒程度実施します。
C膝蓋下脂肪体へのマッサージ
目的:膝蓋骨下方の柔軟性改善
1.膝を伸ばして座ります。
2.膝蓋骨のすぐ下の脂肪体を手で挟み左右へ動かします。
20-30秒程度実施します。