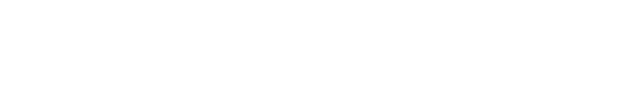腰部脊柱管狭窄症とは
1.腰部脊柱管狭窄症とはどんな病気ですか?
腰部脊柱管狭窄症は、脊柱(背骨)の中央を通る脊柱管が狭くなることによって、神経が圧迫され、痛みやしびれ、運動機能の低下を引き起こす病気です。特に、腰椎(腰の部分)の脊柱管が狭くなるため、「腰部脊柱管狭窄症」と呼ばれます。
2.どんな症状が出ますか?
腰部脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管(脊髄が通る管)が狭くなり、神経を圧迫することで痛みやしびれ、運動障害を引き起こします。この疾患には、神経が圧迫される部位や症状に応じていくつかの型があり、その中でも馬尾型、神経根型、混合型の3つがあります。
日本整形外科学会パンフレットより引用
①馬尾型
馬尾型では、脊柱管の中で馬尾神経(脊髄の終わりの部分で、多くの神経が束になっている部分)が圧迫されます。この型は、以下のような特徴的な症状を引き起こすことがあります。
・両側の足の痛みやしびれ:片側だけでなく両側に広がることが多いです。
・下肢の筋力低下:歩行が困難になることがあります。
・排尿・排便障害:重度の場合、膀胱や直腸の機能が影響を受けることがあります。
・会陰部のしびれ:会陰部(座った時に鞍に当たる部分)の感覚異常が現れることがあります。
②神経根型
神経根型では、脊髄から分岐する神経根が圧迫されます。この型は以下のような症状を引き起こします。
・片側の足の痛みやしびれ:片側の下肢に症状が現れることが多く、坐骨神経痛のような痛みが典型的です。
・特定の神経領域に限定された感覚異常:神経根がどの部位で圧迫されているかによって、痛みやしびれが現れる部位が異なります。
・動作時の痛みの悪化:腰部後屈、前屈などの特定の動作や姿勢で痛みが増すことがあります。
③混合型
混合型は、馬尾型と神経根型の両方の症状が同時に現れるタイプです。つまり、馬尾神経と神経根の両方が圧迫されるため、症状が複雑になります。
3.どんな治療をしますか?
◎薬物療法
①リマプロスト(オパルモン)
血管平滑筋に直接作用して末梢血管を拡げるほか、血小板の凝集を抑制することにより血流を改善し、手足のしびれや痛み、冷感などの症状を和らげます。
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021では、エビデンスの強さは1番高いAとなっています。
②カルシウム(Ca2+)チャネル α2δ リガンド(現在は第3世代タリージェが主流)
痛みやしびれに対して鎮痛効果があり、睡眠の質や痛みに伴う抑うつ、不安も改善することが示されており、痛みだけでなく生活の質(QOL)の改善させる。
神経傷害性疼痛 薬物療法ガイドライン 改訂第2版 第一選択薬として推奨されています。
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021において、「薬物療法」は、エビデンスの強さは2番目に高いBとなっています。
③その他
トラマドール、SNRI(サインバルタ)、三環系抗うつ薬などガイドラインで推奨されエビデンスがある薬剤や漢方を、痛みの専門医が症例ごとに最適な薬剤を選択します。
◎リハビリテーション
リハビリテーションは、脊柱管内の神経の圧迫を改善させる様々な運動療法を行います。
(※どの疾患にも言えることですが、個々の状態に応じて理学療法士の指導のもとで行うことが重要です)
①脊柱管内の神経の圧迫を改善、および姿勢改善させる自主トレーニングはこちらになります。
「腸腰筋ストレッチ」、「膝抱えストレッチ」をご確認ください。
「膝抱えストレッチ」が、特に重要になります。
②脊柱管にかかる負担を軽減させる腰部、腹部の筋力強化の自主トレーニングは、こちらになります。
重要なエクササイズ 「Bird&Dog」をご確認ください。
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021において、「リハビリテーション(運動療法)」は、エビデンスの強さは2番目に高いBとなっています。
◎注射療法
①ブロック療法
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021において、「ブロック療法は短期間の疼痛軽減やQOL改善に有用」であり、エビデンスの強さは1番高いAとなっています。
②硬膜外ブロック
慢性疼痛診療ガイドラインにおいて、「腰部脊柱管狭窄症に対する経椎弓間硬膜外ブロック」の有効性は、エビデンスの強さは3番目に高いCとなっています。
③神経根ブロック
慢性疼痛診療ガイドラインにおいて、「腰部脊柱管狭窄症に対する神経根ブロック」の有効性は、エビデンスの強さは3番目に高いCとなっています。
④椎間関節ブロック
慢性疼痛診療ガイドラインにおいて、「慢性腰痛に対する椎間関節ブロック」の有効性は、エビデンスの強さは3番目に高いCとなっています。
★当院では、各神経ブロック、ハイドロリリースをエコーとレントゲンをガイドにして、経験のある「痛みの専門医」が行います。(※施行する術者によって、効果が変わります)
※難治例の場合、Raczカテーテルによる硬膜外癒着剥離術の適応あります。
◎手術療法
症状が重度で、保存療法で改善が見られない場合には手術が検討されます。
手術療法として、圧迫されている神経を解放するための脊柱管を広げる「除圧術」、脊椎に不安定性を有する場合には、必要に応じて「固定術」が行われます。
どちらも腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021では、エビデンスの強さは2番目に高いBとなっています。
参考)手術後の予後
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021では「腰部脊柱管狭窄症の術後の理学療法は、術後3カ月での痛みやADL/QOL改善に有用であり推奨する」とされています。エビデンスの強さは2番目に高いBとなっています。
→当院で、術後のリハビリテーション治療を受けることができます。
4.予後について
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021では「保存療法の予後」についての記載はないですが、慢性腰痛に対する集学的治療の有用性についての記載があり、慢性疼痛診療ガイドライン(2021年発行)では「集学的治療をすることを強く推奨する」とされています。エビデンスの強さは1番高いAとなっています。
※集学的治療→投薬、神経ブロック、リハビリテーションなどを合わせる治療
★当院では、投薬と神経ブロック、リハビリテーションにて徹底的に治療し、必要であれば外科的治療(手術)も検討していくというスタイルを一貫しています。
2014年のCochraneレビューによると、慢性腰痛に対する「リハビリテーションあり」の集学的治療は、「リハビリテーションなし」の一般治療と比較して、鎮痛や日常生活障害の改善に優れるとしています。 (Kamper SJ,Cochrane Database Syst Rev 2014)